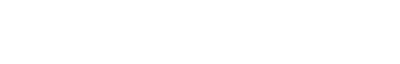政治とは、この世の現象として現れてくる具体的な活動ですが、そのもとにあるものは、やはり、何といっても、政治哲学、理念、あるいは基本的なものの考え方や価値観です。そういうものが投影されて、現実の政治的な活動になってくるわけであり、その意味で、政治思想、政治哲学というものは非常に大事です。このバックボーンのところが、どういうものであるかによって、現実に現れてくる活動や行動が大きく変化してくるのです。
※以上『政治の理想について』より抜粋

▼ POINT ▼ クリックすると該当箇所へジャンプします。
● 関税政策がトランプ外交の一環
● 就任直後から怒涛の関税ラッシュ
● アメリカの貿易収支
● 若きトランプの主張
● 外交交渉の材料としての関税
● 今、読み返したい この一冊!
報道
海外メディアによれば、トランプ大統領は新たな関税措置を発表。米国内に製造工場のない医薬品メーカーの医薬品(ジェネリック医薬品は除く)の輸入に、100%の関税を課す方針を示した。アメリカの製造業者を海外からの輸入医薬品から保護する目的があるとしている。「BBC 2025.9.25」
関税政策がトランプ外交の一環
第二次トランプ政権が発足して以来、関税措置という衝撃が世界中を戦々恐々とさせている。メディアはもとより、世界中の経済学者も反対論を展開しているが、トランプ関税は本当に無謀な政策なのだろうか。実はここにトランプ外交という巧みな戦術が見え隠れする。
就任直後から怒涛の関税ラッシュ
トランプ大統領は就任直後の2025年1月に、カナダ、メキシコ、中国に対して関税をかけた。これは不法移民や合成麻薬「フェンタニル」の流入を問題視しての措置だと説明されている。確かに、メキシコを中心とする中南米からの不法移民の犯罪率は高く、同国の麻薬カルテルと中国の化学メーカーが元凶にある「フェンタニル」によって、全米で年間約7万人が死亡していることから、事は重大である。引き続き、3月には鉄鋼やアルミ、自動車などの特定品目に関税がかけられ、日本自動車には25%の関税が課されることになった。さらに4月には全世界に一律10%の関税を課すという過激な発言が世界を震撼させた。
アメリカの貿易収支
トランプ大統領の思惑を類推するに、関税の引き上げは経済的には不利になるが、アメリカにとってはプラスと考えているのではないか。その根底には「輸出を増やし、輸入を制限し、貿易赤字は出さない」という彼の深い洞察がある。そもそもアメリカの貿易収支を見ると、2024年の輸出額は2.1兆ドル、輸入額は3.35兆ドルで、貿易赤字は約1.3兆ドルに及んでいる。
若きトランプの主張
かつてアメリカ経済の中枢にいたトランプ大統領だが、1980年代に、CNNのインタビューに答え、次のように主張している。「アメリカ人の多くが、自国が外国から搾取されているのを見ることにうんざりしている」と。そして、アメリカが、数十年にわたって外国から富(お金)を奪われ続けているため、関税という政策が、その状況を逆転させる手段だと考えていたのだ。1980年代、製造業をリードしていた当時の日本が、そのターゲットであったことは言うまでもない。日本の製造業に圧倒されたアメリカでは、自動車産業などで職を失う人が後を絶たない状況だった。三菱地所がロックフェラーセンターを買収したという案件も、不動産王トランプにとっては面目を潰された一つの記憶なのだろう。
外交交渉の材料としての関税
トランプ大統領の関税交渉は、貿易における非相互待遇がもたらす不安要素が解決されるまでという条件があるため、単に関税率を上げることが目的ではなく、外交上の交渉材料にしていることは明白だ。また、そもそもグローバル化や自由貿易が、人々に利益をもたらしたかどうかということも疑問である。なかでも先進国の中間層の大多数が、税金の負担が増え、グローバル化の恩恵にあずかっていないと回答している。グローバル化や自由貿易がもたらしてきた負の側面に目を向けることが、日本にとって未来の方向性を決める重要な要素ともなるだろう。
文責:木藤文人(ジャーナリスト)
今、読み返したい この一冊!
1.『繁栄への決断』
―「トランプ革命」と日本の「新しい選択」―
/大川隆法(著)
/1,650 円(税込)
(2016年12月発刊)
〈本文より抜粋〉
※経済面における「トランプ革命」の一つであると言えます。ただ、これが成功するかどうかについては、現時点では、多くの識者たちにはまったく分からない状態にあるでしょうが、私は、「実験する価値は十分にある」と思っています。この二十五年間での米中における問題として挙げられることは、中国が対米に関しては非常に緩い基準でもって多額のドル預金、さらに米国国債を持ってしまい、米国の政治を揺さぶれるまでの力を持つに至ったということがあります。これに対し、トランプ氏としては、おそらく、まずは中国が持っているドル債券、アメリカから儲けた部分を減らそうとするでしょう。これは、軍事的な戦い以前の、いわゆる“兵糧”の問題です。兵糧戦であるため、「そう長くは戦えず、大きな戦いができないようにさせよう」としているのだと見ています。そのように、発想は経営者でありながら、「軍人としての発想」もしっかりと持っていると思われます。「まずは兵糧攻めからする」というのは、戦わずして勝つ方法の一つです。要するに、「アメリカとの関係が悪くなると、中国が赤字になることだってありえる」という状態に持っていくことで、もう少し交渉ができるようになったり、言うことをきくようになったり、あるいは、「人権外交」などと言っても内容が通じる国になる、というような考えなのでしょう。
(PP.136-137)
※二国間貿易は国の関税自主権で調整すべきだというトランプ大統領の政策について、大川隆法総裁のコメント
メールマガジン『時事メルマガ』は、
2025年3月1日から配信を開始しました。
※月1回で配信中!
大川隆法著作シリーズから、主に政治、経済等を学べる書籍を紹介しています。
ぜひ、購読してみませんか。
メールマガジンの登録はこちらへ