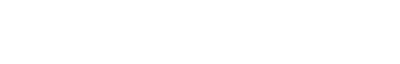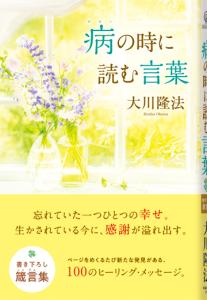病の時は、反省と感謝のとき(#2)
◆━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 2┃ドクター秋子の「ちょこっと健康法」:薬膳料理と健康(2)
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ ビジテイング・プロフェッサーの片岡秋子さんのコラムをお届けします。

前回は、食材には体を温めたり、冷やしたりする性質があり、「五性」といって大きく五つに分けられることを学びました。そして、〝食材の効果を理解する〟ことの大切さをお話ししましたが、今回も引き続き、「未病」を改善していくための「薬膳」について学んでまいりたいと思います。
五臓六腑という言葉がありますが、「五臓」とは、「肝臓」、「心臓」、「脾臓」、「肺臓」、そして「腎臓」のことを指します。「臓」は、人間が生きていく上で、必要なものを蓄えるという機能があります。それぞれの役割として、「肝臓」は気や血の流れをコントロール、「脾臓」は消化吸収機能、「肺臓」は呼吸機能、「腎臓」は体内の水分代謝などをコントロールし、「心臓」が五臓すべてをコントロールしています。一方で「五味」というものがあり、「酸味」、「苦味」、「甘味」、「辛味」、「鹹味(かんみ:塩辛い味)」があり、その五つの味はそれぞれに「五臓」と対応しています。
例えば、「酸味」の場合、「肝」の働きを促進し、下痢や汗、咳などを止める働きがあります。「苦味」は「心」の働きを促進し、解熱作用などがあります。「甘味」は「脾」の働きを促進し、食欲増進や、解毒作用があります。また、「辛味」は「肺」の働きを促進し、気の巡りを良くして発汗作用などもあります。さらに、「鹹味」は「腎」の働きを促進し、便秘や腫れ物を改善する作用があります。
もともと「五臓」や「五味」は、自然界を五つに分類する「五行」という考え方に基づいています。自然界に存在する物質を「木、火、土、金、水」という性質に分けたもので、諸説ありますが中国の『書経』によるとされます。いずれにせよ、こうした古来の智慧に学び、より健康的な食生活へと調えたいものです。
看護学博士:片岡秋子
◆━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 3┃心に問いかける一言:7つ目
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(9) 今という時代に、生命を授かったことを感謝しよう。
メールマガジン「心が変われば、身体も変わる ヒーリング」は、2023年12月15日から配信を開始しました。※3か月毎に1回にて配信中!
大川隆法著作シリーズから、主に病気克服を学べる書籍を紹介しています。
ぜひ、購読してみませんか。メールマガジンの登録はこちらへ