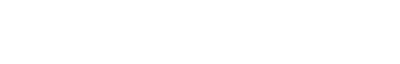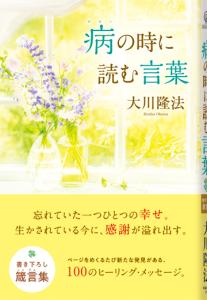病の時は、反省と感謝のとき(#2)
◆━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 2┃ドクター秋子の「ちょこっと健康法」:薬膳料理と健康(1)
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ ビジテイング・プロフェッサーの片岡秋子さんのコラムをお届けします。

日本には「医食同源」という言葉があります。健康な体の源になるのは、「食」であるという考え方から、「食養生」とも言われます。食材にも薬と同じように体を癒す効果があるということで、とくに季節の「旬」のものが良いとされます。体に病気の症状が現れていなくても、体のバランスが崩れている状態を「未病」と言いますが、これを改善していくために「薬膳」があるのです。「薬膳」料理といっても、なにも特別な食事ではありません。旬の食材をいただくことで、その季節に応じた効能が得られるという考え方です。
「薬膳」を食生活に取り入れる上で、大切なことは〝食材の効果を理解する〟ことです。
食材には温めたり、冷やしたりする性質があり、「五性」といって大きく五つに分けられます。「寒性」には、消炎作用があるとされ、アサリ、昆布、スイカ、トマトやバナナなどが挙げられます。「涼性」は、微熱やのぼせの改善に良いとされ、蕎麦、キュウリや茄子、りんごやセロリなど。「平性」はバランスのよい食材で、お米(うるち米)やキャベツ、豚肉やにんじん、鱈など。「温性」は、体を温める食材、冷えによる食欲不振の改善、血のめぐりを良くしてくれます。食材としては、みかん、ニラ、玉ネギ、シャケ、鶏肉などが挙げられます。そして、より温める力が強いのが「熱性」で、発汗や興奮作用などを伴い、女性の冷え症などに良いとされます。(干した)生姜、シナモン、唐辛子、羊肉などが代表的な食材です。
旬の食材の基本的な知識があれば、身近にある食材で、十分に「薬膳」を食事に取り入れることができます。
看護学博士:片岡秋子
◆━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 3┃心に問いかける一言:6つ目
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(33) 自分は、誰かの人生にお役に立っただろうか。
メールマガジン「心が変われば、身体も変わる ヒーリング」は、2023年12月15日から配信を開始しました。※3か月毎に1回にて配信中!
大川隆法著作シリーズから、主に病気克服を学べる書籍を紹介しています。
ぜひ、購読してみませんか。メールマガジンの登録はこちらへ