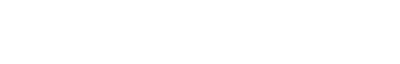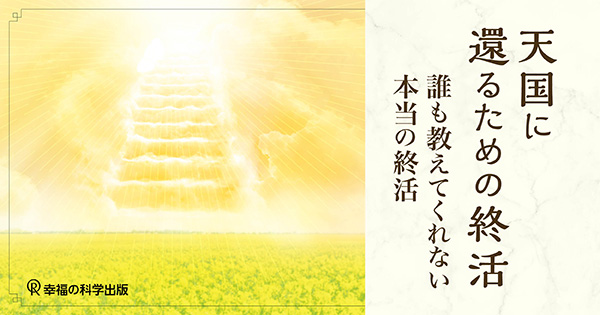┃ 誰も教えてくれない本当の終活
終活ブームの始まりは、2010年前後の日本の社会状況が背景にあると言われます。少子化、核家族化、長寿社会の到来、さらに離婚率の増加も一つの要因です。
また、幸福の科学をはじめとした宗教の社会啓蒙により、人生観や死生観が変化しました。さらに、東日本大震災や近年のコロナ渦も、「死」を見直すきっかけになったと言えるでしょう。
ただ、今の「終活」が、この世的な手続きだけに終始している点は残念でなりません。
本当の終活とは、あの世の世界のことを知り、この世に執着を残してしまうことで家族に迷惑をかけることのないよう、心の備えをすることです。
「天国に還る」ための終活を、ともに考えてまいりましょう。
◆◇目次◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 天活シリーズ:お葬式・お墓事情(1)「樹木葬」編
2 終活コーディネータによる「されど終活」:「遺言、事業承継」編
3 天国に還るための「反省」のすゝめ:『心の挑戦』より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 1┃天活シリーズ:お葬式・お墓事情(1)「樹木葬」編
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━
巷では「樹木葬」を“自然”あるいは“自然に還る”というワードに結びつけて、人気が高まっているようです。その定義とは、一般的に遺骨は墓石に下に埋葬するというのが通常ですが、樹木葬では樹木がお墓の印としての役割を果たします。概ね二つの種類に分かれ、一つは自然の地形を活かして埋葬する「里山型」、もう一つは和風や西洋風の庭のような体裁の「庭園型」があると言われます。最近では「土に還る」というコンセプトのもとに、ペットとともに入れるような共葬というのもあるそうです。
ただ、「樹木葬」には問題が少なくないようで、区画が故人ごとに分けられていないケースも多く、納骨後の遺骨の取り出しができません。また、樹木葬の多くは、「埋葬期間」が決められていて、期間が過ぎれば合祀墓へと移動されてしまいます。そうなれば、基本的なお墓参りや法事ができないことになります。さらに、歳月とともに樹木も成長、枯衰(ほろび)があるため、定期的な剪定や保護などが必要とされ、維持費用が思わず高くつくこともあるようです。自然災害が少なくない山地では、土砂崩れなどで景観が変わってしまうこともあります。
幸福の科学の仏法真理によると、お墓は亡くなった方への感謝や供養の思いを届けるための“アンテナ”のような役割をしていると言われます。つまり、お墓や遺骨がない場合、あるいは歳月を経て、その所在が明らかでない場合は、きっかけとなるアンテナがない状態なので、供養しようにも供養する場所がありません。安易に「死んだら何もかも無くなってしまう」という唯物論的な考えのもとで樹木葬などを行うと、先祖への思いも伝わらなくなってしまいます。
先祖のなかには、子孫たちの暮らしを気にかけて、お盆の供養や墓参りを待ち望んでいる方もいるそうです。宗教を排除して、霊的世界のことなどに関心を向けない“この世的な終活”は、結果として、あの世の不幸をつくってしまう危険性があるのです。
*** 参考文献 ***
。:*:☆。:*:☆。:*:☆。:*:☆。:*:☆。:*:☆。:*:☆───★
〈本文より抜粋〉
西洋・東洋において姿形はいろいろと違うものの、お墓には一種の“アンテナ”のような役割があります。要するに、お墓参りをするなり位牌を祀るなり、そうした供養のスタイルを取ることによって、天上界や地獄界にいる亡くなった方と心が通じる交差点になるところがあるのです。(中略)
普通の人は霊能者ではないので、「思ったらすぐに死者に通じる」ということは、あまりありません。しかし、例えば、「お盆なら、きちんと供養される」「命日には供養される」と、亡くなった人が期待しているような場合に、遺族に供養しようという気持ちがあって、霊園、墓地のように決まった所で供養をすると、その気持ちがつながるのです。両方の電話がつながるような感じになり、お互いの気持ちが通じることがあるわけです。(中略)
ときどきは子孫のことも思い出し、「どうなっているかな」「どうしているかな」と気にしている方もいます。そういうときに、やはり、先祖供養や何かの儀式等で出会える場があると、懐かしく思い出すことができるわけです。(中略)
その意味では、自分の家族などが生きている間は、この世とコンタクトするための何らかの方法が残っているほうがよいということです。
(PP.134-137)
★───☆:*:。☆:*:。☆:*:。☆:*:。☆:*:。☆:*:。☆:*:。
| 著者プロフィル |
|---|
| 大川隆法(おおかわ りゅうほう) 幸福の科学グループ創始者兼総裁。 1956年、徳島県に生まれる。東京大学法学部卒業。81年、大悟し、人類救済の大いなる使命を持つ「エル・カンターレ」であることを自覚する。86年、「幸福の科学」を設立。信者は世界174カ国以上に広がっており、全国・全世界に精舎・支部精舎等を700カ所以上、布教所を約1万カ所展開している。著作は42言語に翻訳され、発刊点数は全世界で3150書を超える。また、28作の劇場用映画の製作総指揮・原作・企画のほか、450曲を超える作詞・作曲を手掛けている。 |