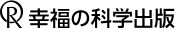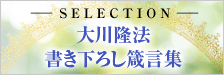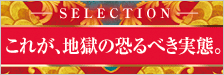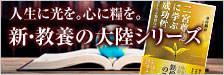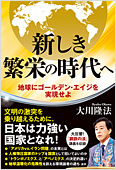2025年05月01日
【時事メルマガ】アメリカ議会下院が、トランプ政権1期目に導入した大規模減税の延長を盛り込んだ予算案を可決
政治とは、この世の現象として現れてくる具体的な活動ですが、そのもとにあるものは、やはり、何といっても、政治哲学、理念、あるいは基本的なものの考え方や価値観です。そういうものが投影されて、現実の政治的な活動になってくるわけであり、その意味で、政治思想、政治哲学というものは非常に大事です。このバックボーンのところが、どういうものであるかによって、現実に現れてくる活動や行動が大きく変化してくるのです。
※以上『政治の理想について』より抜粋
▼ POINT ▼ クリックすると該当箇所へジャンプします。
● 日本政府は今こそ「減税」へと舵を切るべし
● 減税効果を証明した「レーガノミクス」と「サッチャリズム」
● 米国は「減税」とともに「小さな政府」を目指す
● 「お上頼み」から「自助論」へ
● 今、読み返したい この一冊!
❚ 報道
アメリカ議会下院は、トランプ政権1期目の2017年に導入した大規模減税の延長などを盛り込んだ予算案を可決した。予算案では今後10年間に約5兆ドルの減税と、約5兆7000億ドルの連邦政府債務の増加を見込んでいる。「REUTERS 2025.4.10」
ロイターの記事は、加えて「財政調整措置」という手法で、上院の議事妨害を回避し、トランプ大統領の掲げる減税政策などを民主党の協力なしで可決することが可能になると報じた。また、米議会共和党は28日、トランプ大統領の減税政策を盛り込んだ法案の7月4日までの成立に向けて本格的な取り組みを開始した。
長らく経済の低成長が続く日本。三十年を超える停滞のなかで、今、やるべきは「減税」しかない。誰しもが「大きな政府」、お上(かみ)頼みをよいことに、自民党という一党独裁政権は、増税を繰り返し、そのお金をばら撒くという手法で国民を手懐けてきた。今、実感する物価高のなかで、国民はようやく政府の大噓に気づき始めている。昔で言えば、そろそろ一揆が起こっても不思議ではないという様相だろうか。
❚ 減税効果を証明した「レーガノミクス」と「サッチャリズム」
「減税」が実際に効果的だったことを証明したのが、「レーガノミクス」だ。税率を上げすぎることで、国民が税金逃れをしはじめたり、節税に励み出したりする転換点がある。そのあたりを示したのが「ラッファー曲線」というが、レーガンは税率を下げて税収を増やそうと試みた。彼の所得減税策は、アメリカ国民が自由に使えるお金を大幅に増やし、景気を良くしたのは事実である。公約にしていた「小さな政府」は実現しなかったが、軍拡競争をやめなかったことで冷戦を終結させてしまったことは大きな成果だった。
もう一つは「サッチャリズム」である。イギリスは労働党が政権を担うと社会主義的な考え方が強くなり、総じて「大きな政府」を目指す。補助金漬けの政策が増え、国民は政府に頼ってしまう。いわゆる「イギリス病」の蔓延で、かつての大英帝国が国力を失った時代だ。それに対して果敢に挑んだのが、サッチャーその人だった。補助金を大胆にカットし、「小さな政府」を目指した。そのもとになったのが、『隷属への道』のフリードリヒ・ハイエクの思想である。国家が国民の面倒をすべて見るというやり方は、一見、やさしいように見えて、実は奴隷への道、死への道につながっているというものだ。レーガンとサッチャーは15歳という年齢差はあったが、お互いに尊敬し合い、理解し合う仲だった。その根底にあったのが、二人とも幼少期からキリスト教を深く信仰していたところ。おそらく、宗教的な教養をもとに「善悪を判断する」基準を持っていたものと推測できる。
トランプ大統領がめざすところは「安い税金」と「小さな政府」だ。政府効率化省(DOGE)のトップとして起用されたイーロン・マスク氏は、米国連邦予算の2兆ドル規模のコスト削減を目指しているという。「大きな政府」のままでは、財政赤字から抜け出すことができず、補助金頼みでは人は堕落してしまう。
再び、日本の政治に話を戻そう。古くから日本人の間には「お上頼み」という言葉がある。行政が上位にあり、庶民が下位にあると考えている人が多いため、問題が起きるとお上に解決を求め、お上の言われた通りに振る舞おうとする。その傍らで、自分たちは責任を放棄し、また、思考を止めてしまった。
この江戸時代の風潮そのままに、今の時代も国民は考えることをしなくなった。悪代官さながらの政治家が悪いとは言え、彼らを選んだ国民にも責任の一端はある。明治時代、サミュエル・スマイルズの『自助論』は、日本で『西国立志編』として邦訳出版され、100万部以上売れた。そして、多くの小学校で修身の教科書として愛読された。このなかで説かれた「天はみずから助くるものを助く」という思想が、明治期以降の日本の発展に寄与し、敗戦後の日本の復興を促した精神である。今こそ、日本国民は政府に頼らず、自助努力の精神を取り戻すべき時である。
江戸時代の狂歌に次のようなものがある。「今の世の お上はきつい喘息で 昼も税税(ぜいぜい) 夜も税税(ぜいぜい)」。もういい加減、「増税増税(ぜいぜい)」言うのは止めたらどうだろうか。
〈本文より抜粋〉
いちばんの問題は、今の政府が「大きな政府」を志向しているということです。これが問題だと、この十年間、言い続けてきているのですが、意味を分かってもらえないようです。そして、国民のほうも、「政府に何をしてもらえるか」ということばかりを言います。マスコミのみなさんもたいへん親切な人たちばかりなので、「そうだ、そうだ。もっと政府は援助すべきだ。助けるべきだ。タダにすべきだ」ということをしきりに言ってきます。そうすると、だんだん、だんだん、“バラマキ財政”というものが大きくなってきます。(中略)
「大きな政府」というのは、自分たちの力を増していこうとします。したがって、税金も多いほうがいいし、国民に対する景気対策なども大きければ大きいほど効果があるわけです。
(PP.22-23)
〈本文より抜粋〉
「まず、自分ができることは何なのか」「自分の考え方を変えることによって道は拓けないか」―まず各人、それぞれが、そういうふうに考えていくようになったら、町の零細企業、中小企業たちにも、「赤字から黒字に変えることは善なのだ」「黒字は善で、赤字は悪。黒字だからこそ税金を納めることもできるし、それが正当な黒字ならば、世の中の役に立って発展しているという証拠でもあるのだ」ということです。そういう考え方を持つようにしようではありませんか。(中略)
「自助論」の考えは厳しいから、みんなが嫌がるけれども、それがやはり、産業革命以降、ヨーロッパの国やアメリカが成功した理由ではあるのです。今、その成功が止まろうとしつつあります。社会福祉的な考えで、「すべては社会悪によって貧困が生まれて、犯罪人が生まれて、経済的にも成功しないんだ」という考えになってきたら、これはお金を撒くだけの仕事が発生します。そうすると、先ほど言った偽金づくり、偽金撒きみたいな方向に行きかねないことが多いので、人間の魂まで曲がっていく傾向があると思います。
(PP.89-92)
| 企画、構成 編集者プロフィル |
|---|
| 木藤文人(きどうふみと) ジャーナリスト、宗教家。 大学を卒業後、大手広告代理店に勤務。フリーとして独立後、「週刊東洋経済」「プレジデント」「経済界」「ザ・リバティ」等の執筆を経て、2007年、幸福の科学出版に入局。『天国に還るための終活』等、編著も多数。 |
◎メールマガジン『時事メルマガ』は、2025年3月1日から配信を開始しました。※月1回で配信中!
大川隆法著作シリーズから、主に政治、経済等を学べる書籍を紹介して参ります!
ぜひ、購読してみませんか。メールマガジンの登録はこちらへ≫